ぼんやりとした意識の中で誰かに声をかけられた気がした。
うっすらと目を開きながら木ノ前すみれはまた机に突っ伏したまま寝てしまったことを後悔した。
ちゃんとベッドで寝ればよかった。
腰痛のリスクを自ら高めてしまったかもしれない。
突っ伏す目線の先の置き時計は朝の五時前、四時五〇分を指していた。
間もなく日の出を迎えるのか部屋は薄明るい。
明るい?
木ノ前すみれは少し不思議に思った。
確か、カーテンは閉めたはずなのに。
そう思ってすぐの事だった。
室内に春、と言っても朝はまだ肌寒い風が吹き込んできた。
窓は開けてない!とガバっと体を起こして窓の方を向いた時だった。
開いた窓枠に少女が一人、腰かけていた。
そこで木ノ前すみれの眠気は完全に吹き飛ばされた。
「……!?」
なんだあれ。
あれ、と表現したのは少女の姿はしているが、少女のようで少女ではない印象を受けたからだ。
正体不明の存在に身の毛がよだつ。
その理由(ワケ)は少女の瞳にあった。
瞼(まぶた)、まつ毛、瞳孔(どうこう)、そういった瞳という人間の部位を構成しているその全てが、まるでヨーロッパの教会に設置された色鮮やかすぎるステンドグラスのようになっていた。
いや、それ(ステンドグラス)よりも無数に煌めく宝石のような瞳と表現すべきかもしれない。
その姿に木ノ前すみれの心拍数は跳ね上がった。
宝石瞳の少女を前に棒立ち、いつまでも眺めていることはできない。
この部屋から出て距離を置かなければ。
何か声を上げなければと恐怖する。
「……、……!……!?」
しかし声は出なかった。
あまりの恐怖に声が出なくなったのではない。
両手で喉(のど)に触れるも息を止められたわけじゃない。
出してはいるが全く響かない。
まるで枕に顔を押し当て声を出しているかのような、それ以上に自分の声だけが全くの無音であった。
この場から逃げなければ。
木ノ前すみれは扉のドアノブに手をかけ手前に力いっぱい引いた。
しかし扉は開かなかった。
全く扉に動きはなく、鍵付き扉ではないのに鍵付き扉のように何度開けようとしても扉は固く閉ざされていた。
極度の緊張感と共に木ノ前すみれはどうすることもできず、扉に背中を預けてそのまま床にへたり込む。
どうすることもできない時、息子の姿が頭によぎった。
自分よりも今、息子は大丈夫か。
もはや動くことはできない。
宝石瞳の少女が近づいてくる。
季節外れの白いワンピースに、足元は何も履いておらず裸足だ。
年齢(とし)は息子より下だろう。
──────そして。
「びっくりさせてごめん、すみれ。もうすぐ解(わか)るから」
「は────、」
とクエスチョンマーク(?)が頭に浮かぶ前に木ノ前すみれは何の前触れもなく理解した。
目の前にいる宝石瞳の少女が大切な友達であることを。
かつて異世界『ログフィール』において大陸を巡り歩き、旅をしたかけがえのない仲間であったことを。
【#9に続く】


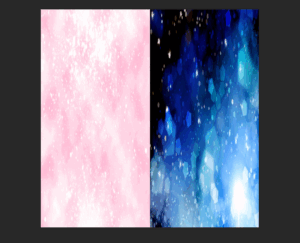
ログフィール!?まさかの展開!
#9も期待してます!!
コメントありがとうございます。
そのお言葉に感謝です。「よーし!がんばるぞー!」という気持ちになります。
https://t.me/s/Top_BestCasino/120